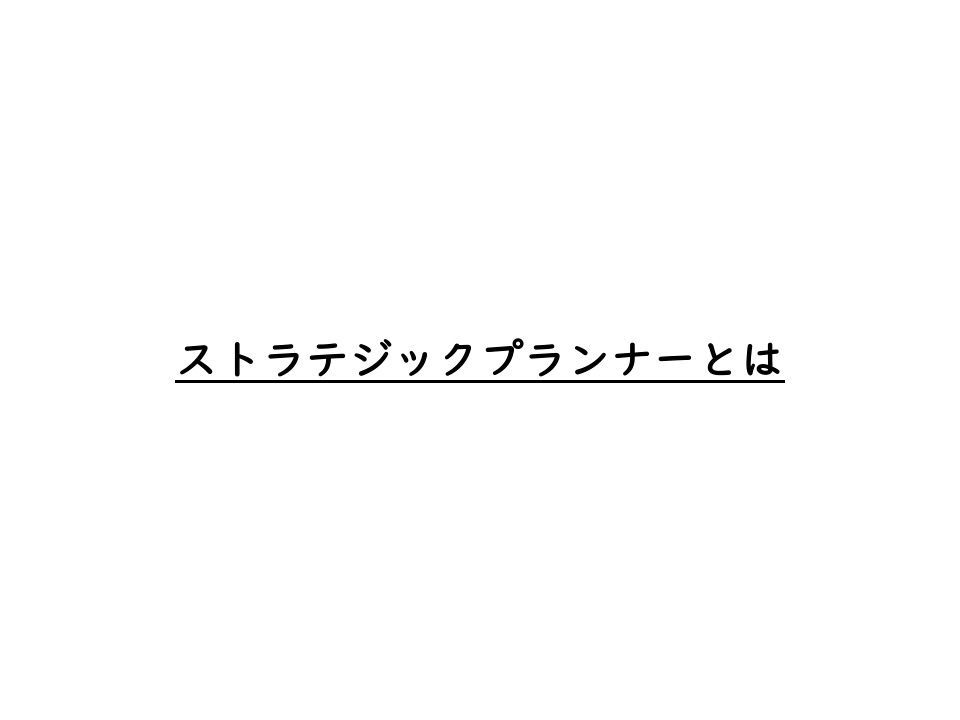建築学部出身なのに、敢えて広告業界を選んだ理由
大学では建築を専攻されていた小川さんが、新卒で広告代理店の東急エージェンシーに就職したのはなぜですか?
小川:大学では、建築のなかでも設計や意匠など図面を引く分野を学んでいました。それはそれで好きでしたが、設計会社に就職して設計だけを担当するのはちょっと違うなと。一口に建築といっても、「設計」と、その前段となる「企画」があり、建物の「運営」があります。僕が目指したのは「企画、設計、運営と建築をトータルでプロデュースできる人間になる」ことで、まずは企画を学ぼうと広告代理店を選びました。
東急エージェンシーでは営業に配属されました。最初は百貨店の催事のチラシなど比較的地味な案件ばかり。テレビCMなど派手な仕事を手がける同期を見て「企画をやるつもりで入ったはずなのに、どうしてこんな仕事を…」と悔しく思ったこともあります。でも営業経験はその後めちゃくちゃ役立ちましたね。営業は「チームをつくり、スケジュールとお金の管理をする仕事」です。どんな仕事であれ納期と数字を守れなければ評価されない、それは経営者になった今も意識していることです。
その後、まちづくり事業に関わる事を目的に、九州支社に転勤する決断をされていますね。
小川: もともとまちづくりには興味がありました。それに当時は地方創生の一大ブームで、あらゆる地域が移住者を集めていたんです。「どこでもいいから支社にいかせてほしい」と会社に掛け合うと、福岡にある九州支社が歓迎してくれました。
九州には5年弱いました。1年めは九州支社の既存クライアントを担当させてもらい、2年めから行政案件をとりにいきました。最初の仕事は、佐賀空港のリニューアルに伴うプロモーションやロゴデザイン関連です。熊本県上天草市との仕事も思い出深いです。ロバート秋山さんを起用した上天草市のPR動画が話題になりましたし、観光交流拠点という「建物」づくりに初めて関わりました。
「補助金に頼らないまちづくり」を目指して独立

小川さんが独立に向かうのはそれからですね。
小川: はい。行政の仕事に関わるなかで1つ違和感を持ちました。まちづくり事業の多くは行政からの補助金に支えられています。それはいいのですが、「この予算は映像を作るために支給されているから映像以外には使えない」といった制約にもどかしさを感じました。例えば、「映像より効果のあるコンテンツを作れます」と提案しても、「映像のための予算なので他に振り分けられません」となってしまいます。
そんなモヤモヤを抱えていたとき、補助金を頼らないまちづくりを実現している木下斉さんの著書を読み、「自分の悩みの答えが書かれている!」と感銘を受けたんです。すぐにお会いすると「自治体と民間が連携したまちづくり」を学ぶスクールに誘ってもらえました。
直接的には、そのスクールで得た縁がきっかけで、僕は岩手県紫波町に移住、独立することになります。紫波町でまちづくりをしていた人がスクールで講師をしていたんですね。
もともと独立志向はありませんでした。僕の目標は「企画、設計、運営と建築をトータルでプロデュースできる人間になる」ことで、九州でのまちづくりで学んだことは東急エージェンシーで生かせばいいと思っていました。でもあらためて考えると、運営をするには自分でコンテンツをつくらないといけない。しかし行政からの補助金は自由に使えるものではない。となると、自分自身がリスクをとってコンテンツを立ち上げて運営しながら、必要な支援があればその都度行政からもらうというやりかたが、どうしても必要になります。
東急エージェンシーにも相談しましたが、そんなビジネスは広告代理店の枠内では難しいという結論に至りました。そうして退職し、岩手に移住したのが2019年のことです。
岩手で挑んだ「町が必要とするコンテンツ」づくり

独立の経緯がよくわかりました。岩手ではどんな事業を?
小川:町に必要なコンテンツを自分でつくることから始めました。朝ごはんが食べられる店がなかったので商店街の食堂を朝だけ間借りしてお粥専門店を立ち上げたり、子どもを連れていけるお店が足りないからと町にひとつしかなかった焼肉店を出したり、サウナをつくったり。珍しいところでは動物園の経営もお手伝いしていますね。
どれも未知の領域ばかりで、今も手探り状態です。でも営業時代の「チームをつくり、スケジュールとお金の管理をする」経験はここでも生きています。それから、いざ自分がモノやサービスを売る立場になると「圧倒的なクリエイティブやブランディングがないと売れる形にするのは厳しい」とよくわかりました。広告代理店時代は「なんでこんなに細かく工夫するんだろう」と思っていたことも、経営者になると「こうしないと売れないんだ」と腑に落ちることばかり。まるで「答え合わせ」をしているみたいに、昔抱いた疑問が一つひとつ腑に落ちていきました。

そして「LOSS IS MORE」を創業。どんな思いからスタートしたのでしょう。
小川:LOSS IS MOREは、食材や生花、建材など、世の中に数多ある「ロス」に対価を払い手に入れ、価値のあるプロダクトに生まれ変わらせる取り組みをしています。第一弾の商品は、生花店で廃棄されるカーネーションをつかったクラフトジンでした。
LOSS IS MOREのアイデアを思いついたのはコロナ禍でのことです。あの頃は「あらゆる産業、特にサービス業は必要なロスで成り立っている」ことを思い知らされました。地域に必要とされている以上は、お客さんがいつくるかわからなくても絶対にお店をあけないといけない。焼肉店なら、廃棄が出るとわかっていてもお肉を用意しますし、サウナなら部屋を100度に熱くしておきます。
顧客満足度を高めるため、クオリティの高い商品やサービスを提供するには、ある程度のロスはやむを得ないと覚悟してはいます。しかし、またコロナ禍みたいな事態が起こる可能性があるなら、こうしたやむを得ないロスをキャッシュに変えないと、この先サービス業は絶対に成り立ちません。それなら、ロスをモア(≒キャッシュ)に変えるビジネスをして地域のサービス業、ひいては社会を盛り上げていこう。「LOSS IS MORE」という社名にはそんな思いを込めました。
付け加えると、著名建築家のミース・ファン・デル・ローエの言葉「LESS IS MORE(より少ないことは、より豊かなこと)」にかけた社名でもあります。僕は、ロスが社会を豊かにするといえる社会を作りたい。「ロスを出してはいけない、もったいない」と強迫観念のように思いつめるより、「こんな解決策があるから、ロスを出しても大丈夫」と思える社会のほうが、豊かだと思います。

第一弾の商品カーネーションをつかったクラフトジン『LOSS IS MORE GIN』について詳しく教えてください。
小川:生花店もたくさんのロスが出ます。仕入れの段階で少しでも傷がついていたり茎がまがっていたりすると全部廃棄しないといけない。特に「母の日」が終わると捨てられてしまうカーネーションのロスは大量です。そこでジンに着目しました。ジンは植物由来の原料など「ボタニカル」による香りづけが特徴のお酒です。花を使えば花の香りがするジンがつくれます。しかもジンのような蒸留酒は度数が高く消費期限がありません。「ストーリーがしっかりしているので、お客さんに勧めやすく会話が弾む」と、バーなどから好評です。
※今年は母の日のギフト用に、「LOSS IS MORE GIN」と、同じく廃棄されてしまう予定だったカーネーションをドライブーケに加工し、ギフトセットとして販売する予定とのこと。記事が公開されるタイミングはまさに母の日直前なのでぜひお買い求めください
『LOSS IS MORE GIN』以外にも今年いくつかのプロダクトをリリースされる予定だとか。
今年はとある街で廃棄がでてしまう花をテーマにしたブランデーや農家さんが廃棄に困っている人参をつかったリキュールをローンチ予定です。また、お酒だけでなくほかにも進行中の計画がいくつもあります。
こうした「ロスをモアに変える」ためのアイデアは常に探しています。ロスと呼ばれているものを提供していただける「ロスパートナー」の方がいたら、ぜひご連絡ください。
ちぐはぐに見えるキャリアも「辻褄」を合わせれば財産に

今後LOSS IS MOREをどう成長させたいですか。
小川:まずは売上と利益を安定的に伸ばし、事業で得られたキャッシュを次の「ロス」案件へ即投入できる循環をつくりたいです。ロス解決の相談を受けた瞬間に資金も人手も充分そろっている状態が理想ですね。そう考えると、なんとしてもLOSS IS MOREをある程度のサイズの会社に成長させなければならない、という想いがあります。
自分のスキルでロスを価値化したい仲間も必要です。特に一緒に仕事をしたいと思っているのはデジタル分野の人材です。デジタルに疎い僕の妄想かもしれませんが、世の中には有効活用されないデータや処理能力などの「デジタルロス」もあるはず。たとえば事故多発交差点の監視カメラ映像は、24時間365日稼働しているのに、事故の検証などに活用される機会はわずかです。未利用データを新しい価値に転換できれば、環境負荷の軽減と利益を両立させることができるのではと期待しています。
最後に、広告代理店に転職しようと考えている方へメッセージを。
小川:広告代理店ほど幅広い経験ができる環境はなかなかありません。配属先や担当案件が希望と違っていても、むしろラッキーだと思ってほしいですね。どんな仕事もムダだと思った瞬間にムダになります。でも「この体験を将来どう生かせるだろう」と考えながら仕事をすれば、思いもよらない豊かなキャリアの可能性が開けるかもしれません。僕は建築への興味から広告の道を選び、まちづくり、そしてお酒づくりにたどり着きました。これってすごい話だと思います。人から見たらチグハグなキャリアも、意思と少しの偶然がきっかけで辻褄をあわせれば自分の財産に変わる。キャリアの正解は自分でつくりにいくものだと考えています。